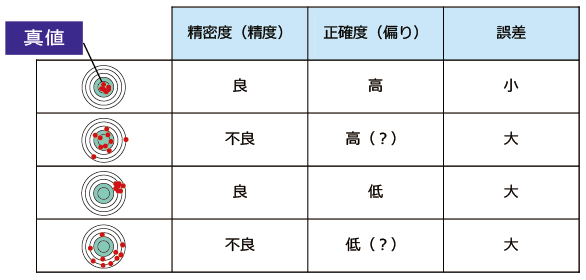Ⅱ. 精度管理の目的(精密性と正確性)
精度管理の目的の1つは、「安定して正確な測定結果を得る」ことにあります。「安定して」とは、「再現性が良い」、あるいは「バラツキが小さい」という言葉に置き換えることもできます。したがって、安定しているかどうかは、再現性やデータのバラツキ程度を評価するのと同じ方法で評価することができます。同一の検体を複数回測定したときに得られる測定値が、ほぼ同じであり安定した測定値が得られている状態を、精度管理では一般に「精密性」が高いと言います。数値としては、多くの場合SD(標準偏差)やCV(変動係数)といった統計量が用いられ、これらの数値が小さいほど精密性が高いということができます。
測定値 = 真値 + 偶然誤差 + 系統誤差
一方正確性は、実際の測定によって得られた測定値(観測値)が、どの程度「真値」に近接しているかを評価することになります。真値とは、検体中に含まれる測定対象物質の真実の値を示す概念ですが、多くの場合真値を知ることは非常に困難です。そこで、多くの場合様々な条件(試薬構成や使用する測定機器、施設など)で測定した場合の測定値を真値に替わる値としてしています。外部精度管理プログラムであるコントロールサーベイで、全参加施設から報告された測定値の平均値を基準として正確性の評価が行われるのはこうした理由によります。測定値は真値に測定誤差を合わせたものと考えることができますので、正確性は誤差の大きさを評価していると考えることもできます。
*「中心極限定理」という統計学的な考えに基づいています。中心極限定理については、統計学の参考書をご参照ください。