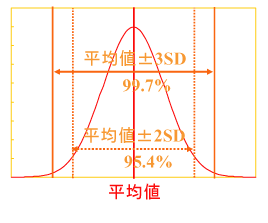Ⅴ-2. 精度管理データの解釈-管理限界と平均値
2. 管理限界と平均値±2SD
精度管理データの管理限界として、平均値±2SDが広く利用されていることはご存知の通りです。しかしながら、この管理幅が意味する点については意外に十分な理解がされていない場合が多いようです。
平均値±2SDという管理幅は、統計学的には全測定値の95.4%をカバーする範囲です。したがって、平均値やSD(標準偏差)を算出する元になるデータや、そのn数が変化すれば、平均値±2SDという範囲自体も変化することになります。さらに、全測定値の95.4%をカバーする範囲ということは、逆にいうと4.6%の測定値(およそ20回に1回の割合で出現)は、この範囲を外れることになります。もしある日の測定結果が平均値+2SDを上回ったとしても、次に測定した結果が範囲内に入るのであれば、測定系自体には問題がなく、系統学的には十分に起こりうるバラツキの範囲内での事象であった可能性もあります。逆に、その日を境に何度測定しても測定結果が管理幅を外れるのであれば、測定結果になんらかの異常が発生している可能性があります。
測定値の管理限界は、こうした統計学的な各数量の意味を十分に理解した上で設定すべきであり、場合によっては平均値±2SDと±3SD、あるいはR(重複測定時の各測定値の差)との組み合わせも考慮して設定すべきと言うことができるでしょう。ちなみに、平均値±3SDは、全測定値の99.7%をカバーします。
図5:平均値±2SDの範囲
平均値±2SDと3SD、あるいは複数測定値から得られるR等の組み合わせにより、適切な管理限界を設定することが重要です。さらには、こうした管理限界を超える測定値の出現頻度や、低値側または高値側への偏りをモニタリングしておくことも大切なポイントです。